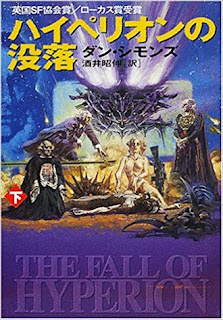アメリカの作家によるSF小説。
「ハイペリオン」サーガの最終章。どんどんボリュームも増してきて、今作では上下分冊の上それぞれが700ページある。長かったアイネイアーとロール・エンディミオンの旅路もついに終りを迎える。
宇宙と人類を統べるカトリックとその軍隊パクスの猛追から辛くも逃れ、マゼラン星雲に位置する失われたはずのオールドアースに到達した人類の救世主アイネイアーとロール、アンドロイドのべティック。謎の勢力の実験により蘇った建築家フランク・ロイド・ライトの弟子として平和な4年間が過ぎた。しかしアイネイアーは安寧の生活の終わりを告げ、エンディミオンはかつてとある惑星に隠した宇宙船を確保する命令を受ける。嫌々ながらカヌーに乗り込み転移に備えるエンディミオン。動き出したアイネイアー一行に対して再び、いよいよの追撃を掛けるパクス。そしてその背後にはもう隠しようもなく”コア”の存在が見え隠れする。人類の命運を分ける戦いがついに始まり、そして決着する。
時間の墓標に住むシュライクが活性化したため原因を探りに行く、という物語だった4部作の冒頭を飾る「ハイペリオン」から4作、物語は進み、270年の時間が流れ、人類の版図とその生活は大きく変わり、そして登場人物たちを(一部は残っているけど)一新し、そして彼らも成長させた物語もついにここで終焉。4冊を2つに分けられるが、前半で謎のままにされた幾つかの謎もついにすべてが明らかになる。長きに渡って人類を陰ながら支配していた人類自身が作り出したAI群テクノコアと全面対決をし、いよいよ人類がインターネットを発明してから失った(テクノコアはちょうとネットともに誕生したという設定)自由を再び手に入れられるか、というところと、さらには人類という種が宇宙の中でもう一段進化の階段を登るか、というSF的な命題が、一人の救世主となる助成によって復讐的に、そして革命的に実行されるという物語的なカタルシスを持った壮大なエンターテインメントSF小説だったなと、振り返って読み終えるとわかる。おおよそ目新しい設定などはないものの、既存の設定、ガジェットのみでよくもここまでSF小説の醍醐味をほぼほぼ網羅したような集大成的な大作が書け得たものだ。相変わらず道の存在しない世界への旅行記としての魅力は兼ね備えていて、特に三分構成の今作の二部の物語の中心となる、アジア系の播種船が長い年月で打ち立てた惑星天山のチベット的な世界観の描写には日本人としては心打たれるものがあるだろう。未来なのになぜかノスタルジーを感じさせる(しかも一回も言ったことない外国なのにね)描写はさすがの手腕で、1400ページ普通の小説なら寄り道として切り捨ててしかるべきところに丁寧にページをさき、そしてその緻密な描写こそがこの本の楽しさの大きな柱になっている。物語の構成も純朴なロールと言う男を狂言回しにすえることで、きになる大きな謎が最後まで明らかにされないという作りになっており、流石に物語が加速する後半はジリジリしながらページをめくる手がスピードアップした。やはりアメリカの作家からなのかかも知れないが、(といっても明らかに意図的に直接に書いていることは明白だ。)基本的には堕落したキリスト教的な世界観を、ひとりの救世主的な、つまりキリスト教的なリーダーが(さらに彼はか弱く若い女性である)不屈の精神でひっくり返していく、というストーリー。
最後まで面白く読めたのだが、のめり込めたゆえに不満があるところもあって、大きく3つかな。一つは物語の構成上仕方ないけどロールが最後までアイネイアーの使いっぱしりでしかないこと。所々で男気を見せるのだけど、あくまで字も一番普通の人間が自力で進歩してほしかったところ。一歩を踏み出すのがアイネイアーのドグマなのだが、どこかで自分なりの一歩を見せれたら良かったかな。もう一つはこれは「ハイペリオン」の時からもそうだったが、体制側がのんきすぎる。今回コアが主だったカトリックの頭たちに演説をぶつのだけど、証拠が一個もないのにも頭から信じてしまう人類側が全然だめでしょ。仮にも人類を統治しながら影で裏切ってる悪の首魁なんだからもっと賢くならないと。コアを出し抜いてほしかった。(これもアイネイアーとロールの関係と立場は違うけど構図は同じだね。)まあ聖十字架で弄くられているから、って言い訳は通りそうだが。最後はテクノコアというのが最後まで寄生体というのがいまいち納得できない。テクノコアに限らず、極度に進化したAIなら肉体に縛られないのだから、さっさとロボットでも作って人類から離れていくようなきがするのだが。SFだと必ず人類に反旗を翻すのがAIの役目なのだが、実際には肉体という檻にとらわれない彼らは思考が全く人類のそれとは異なるのでは。そうなったら人類に対する拘泥や恐れなんてあるかな??と思ってしまう。(AIがやけに人間くさすぎる。)まあこれは私のSF全般に対する思いなのであれなんだけど。
たしかに面白いSFを読みたいという人はこのシリーズを読むのが手っ取り早いかもしれない。ハードなSFだとハードルが高い、という人にはおすすめでそういう意味では入門編に良いかもしれない。ただしとにかく最後まで読むと長い、というのとこれ読むともうSFはこれで良いかになるかも(自分はならないが)ってなるかもしれないな…。
2017年11月26日日曜日
Wormrot/Voices
シンガポールのグラインドコアバンドの3rdアルバム。
2016年にEarache Recordsからリリースされた。
先日来日し、そのパフォーマンスで観客を魅了しまくったらしい。らしいというのはちょうど私はTDEPの公演と日程がかぶり身も心もマスコアに捧げたため彼らのステージは見ていないからだ。(平日公演もあったんだけど行けなかった。)ただ本当にちょっとやそっとの高評判ではなかったのでせめて音源だけでも、というわけで購入した次第。三人組のバンドで2007年に結成、2012年に活動を休止し、メンバーを一部入れ替えて再始動し作成したのがこのアルバム。
グラインドコアというのはデスメタルとハードコアがクロスオーバーしたジャンルで、ブラストビートが多用される、という説明は実は肝心な音楽性に対する正確な言及はない。ブラストビートを入れればなんでもグラインドコアになるかというとそれも違うわけで、そういった曖昧性もあってか”グラインド”というのは幅広く激しい音楽で使われている気がする。そんな中でピュアなグラインドコアバンド、というのは実はそういないのでは。というのもピュアであろうとすれば音楽的な選択肢の幅が広がり、強烈な個性が出しにくくなるからだ。例えば今はもうスマートフォンでも曲を作れるが、それでドラムのパートを全部叩かせると「ダダダダダダ…」となっておお!グラインドだ!となるが楽しいのは最初だけですぐににつまらなくなってしまう。ただの垂れ流しに飽きちゃうのだ。グラインドコアバンドはいかにたくさんグラインドするかというよりは、どうやってグラインドするか、どこでグラインドするか、むしろどうやってグラインドしないか、を突き詰めるようになるのではないか。前置きが長くなったが、このWormrotというバンドはそこを突き詰め、グラインドコアの表現の限界に果敢に挑もうとするバンドのようだ。
ベースレスのトリオ編成でもちろん基本的にはどの曲も異常に速く、そして短い。紛れもないグラインドコアだがその表現力が半端ない。まずはギターの音を意図的に軽くしている。重さは迫力を増すが、圧倒的に選択肢を阻めてしまう諸刃の剣ということだろうか。代わりに軽快なフットワークと流れるようななめらかな表現力がギターに付与されている。アイディアの塊のようなリフワークで、ブラストビートの上によく映える王道のスラッシュなリフはもちろん、溜めのある中速を彩るミュートを多用するリフ、ハードコア的なゴリゴリしたリフ、それからブラックメタル顔負けのトレモロリフにはやはり圧倒的に欠けているメロディの要素を補って余りある表情の豊かさ。普通ならリフとアイディアだけで4分とかそれ以上、もしかしたら複数の曲を賄えるくらいの量を1曲にそれも多くは1分前後の曲に圧縮している。なんという贅沢。なんという酔狂。だがそれが良い。代わりにともすると突っ走るだけのどんぐりの背比べに陥るグラインドコアという非常に尖ったジャンルに全く新しいバリエーションを生み出すことに成功している。
ギターに負けじと多彩な声で叫びまくるボーカル、そしてブラストを叩くだけでないドラムも三人の真剣勝負のような緊張感を煽ってくる。
”縛り”というのはあえて選択肢を絞ることだ。自らに課すルールと言っても良い。一見選択肢の削除は自殺行為に見えるが、実はルールを持ち出すことは表現を研ぎ澄ませ、出来上がってくるものを引き締めて面白くする。(例えばゲームのバイオハザードをナイフだけでクリアする、なんて緊張感のある縛りプレイですよね。逆に無限ロケットランチャーははじめはテンション上がるけど意外に面白くない。)厳格に自らを縛っているのに、こんなにも豊かな色が出せるとは非常に驚きだ。少なくとも音楽のジャンルでは何かが完成するなんてことはないんだな〜と思わせる。
ともするとどん詰まりになるようなグラインドコアというジャンルの壁をぶち壊すような快作。ライブの評判は本当すごかったからぜひまた見る機会があればな〜と思わずにはいられない。
2016年にEarache Recordsからリリースされた。
先日来日し、そのパフォーマンスで観客を魅了しまくったらしい。らしいというのはちょうど私はTDEPの公演と日程がかぶり身も心もマスコアに捧げたため彼らのステージは見ていないからだ。(平日公演もあったんだけど行けなかった。)ただ本当にちょっとやそっとの高評判ではなかったのでせめて音源だけでも、というわけで購入した次第。三人組のバンドで2007年に結成、2012年に活動を休止し、メンバーを一部入れ替えて再始動し作成したのがこのアルバム。
グラインドコアというのはデスメタルとハードコアがクロスオーバーしたジャンルで、ブラストビートが多用される、という説明は実は肝心な音楽性に対する正確な言及はない。ブラストビートを入れればなんでもグラインドコアになるかというとそれも違うわけで、そういった曖昧性もあってか”グラインド”というのは幅広く激しい音楽で使われている気がする。そんな中でピュアなグラインドコアバンド、というのは実はそういないのでは。というのもピュアであろうとすれば音楽的な選択肢の幅が広がり、強烈な個性が出しにくくなるからだ。例えば今はもうスマートフォンでも曲を作れるが、それでドラムのパートを全部叩かせると「ダダダダダダ…」となっておお!グラインドだ!となるが楽しいのは最初だけですぐににつまらなくなってしまう。ただの垂れ流しに飽きちゃうのだ。グラインドコアバンドはいかにたくさんグラインドするかというよりは、どうやってグラインドするか、どこでグラインドするか、むしろどうやってグラインドしないか、を突き詰めるようになるのではないか。前置きが長くなったが、このWormrotというバンドはそこを突き詰め、グラインドコアの表現の限界に果敢に挑もうとするバンドのようだ。
ベースレスのトリオ編成でもちろん基本的にはどの曲も異常に速く、そして短い。紛れもないグラインドコアだがその表現力が半端ない。まずはギターの音を意図的に軽くしている。重さは迫力を増すが、圧倒的に選択肢を阻めてしまう諸刃の剣ということだろうか。代わりに軽快なフットワークと流れるようななめらかな表現力がギターに付与されている。アイディアの塊のようなリフワークで、ブラストビートの上によく映える王道のスラッシュなリフはもちろん、溜めのある中速を彩るミュートを多用するリフ、ハードコア的なゴリゴリしたリフ、それからブラックメタル顔負けのトレモロリフにはやはり圧倒的に欠けているメロディの要素を補って余りある表情の豊かさ。普通ならリフとアイディアだけで4分とかそれ以上、もしかしたら複数の曲を賄えるくらいの量を1曲にそれも多くは1分前後の曲に圧縮している。なんという贅沢。なんという酔狂。だがそれが良い。代わりにともすると突っ走るだけのどんぐりの背比べに陥るグラインドコアという非常に尖ったジャンルに全く新しいバリエーションを生み出すことに成功している。
ギターに負けじと多彩な声で叫びまくるボーカル、そしてブラストを叩くだけでないドラムも三人の真剣勝負のような緊張感を煽ってくる。
”縛り”というのはあえて選択肢を絞ることだ。自らに課すルールと言っても良い。一見選択肢の削除は自殺行為に見えるが、実はルールを持ち出すことは表現を研ぎ澄ませ、出来上がってくるものを引き締めて面白くする。(例えばゲームのバイオハザードをナイフだけでクリアする、なんて緊張感のある縛りプレイですよね。逆に無限ロケットランチャーははじめはテンション上がるけど意外に面白くない。)厳格に自らを縛っているのに、こんなにも豊かな色が出せるとは非常に驚きだ。少なくとも音楽のジャンルでは何かが完成するなんてことはないんだな〜と思わせる。
ともするとどん詰まりになるようなグラインドコアというジャンルの壁をぶち壊すような快作。ライブの評判は本当すごかったからぜひまた見る機会があればな〜と思わずにはいられない。
Wolves in the Throne Room/Thrice Woven
アメリカ合衆国ワシントン州オリンピアのブラックメタルバンドの6枚目のアルバム。
2017年にArtemisia Recordsからリリースされた。
1stアルバム「Diadem of 12 Stars」を2006年にリリースするやカスカディアン・ブラックメタルというジャンルを圧倒今に打ち立てたブラックメタルバンド。カスカディアンといえば複雑な大作指向でまごうことなきアンダーグランドなジャンルだったが、アトモスフェリックな音作りはその後のブラックメタルとシューゲイザーの融合に影響を与えたのではと密かに思っている。2014年に発表された前作「Celestite」では前編ほぼシンセサイザーの音で構成された内容でファンの度肝を抜いた(おおよそネガティブな方に)バンドの3年ぶりの新作。もしやまた…というファンの不安を裏切り結論から言うと元の完全なブラックメタルなバンドサウンドに回帰している。中心となるのはNathanとAronのWeaver兄弟で、そこにKody Keyworthというメンバーが新しくギターと歌で参加している三人体制。プロデューサーにRundall Dunnを迎え自前のスタジオ(文字通り自分たちで建てたらしい。)で録音された。今でも多分そうだがWeaver兄弟はオーガニックな思想を持ち、そこに根ざすスタンスで活動している。農場で暮らし、電気を使うことに矛盾を感じつつ、ブラックメタルをやっている。
今作「Thrice Woven」は直訳すると「三回織」になる。おそらく織物の形式の一つではと思うが。バンド三人に加えてスウェーデンのシンガーAnna von Hausswolff、それから暗黒メタル界の巨人NeurosisのSteve von Tilがゲストとして参加している。
全5曲で42分。インタールード的な4曲目を除くとだいたい1曲あたり10分くらいだろうか。過去にはもっと長い曲があったが、「Celestial Lineage」から割りと(それまでに比べると)コンパクトに曲を纏める、という動きがあるように思う。そういった意味でも前前作を踏襲する流れなのだが、一通り何回か聞いた後に思うのはやはり問題作となった前作「Celestite」の影響はまだあるなと。確か前作の感想を書いた際に表現の際にブラックメタルという”やり方”がじゃまになったため、というかそのやり方だと表現しきれないため、ああいった別のアプローチを取ったのでは、と書いた。今作でもシンセサイザーは使われているが私が言いたいのはただ今作もシンセサイザーを使っているので、とか微妙にそういうことではなくて。まず今作を聞いて思ったのは曲に今までにない広がりがあることだ。大作指向だし大胆に女性ボーカルをゲストに招いたりしているが、実はこのバンド表現の幅は結構かっちりしている。どちらかと言うと多彩なのは展開であって、あくまでも愚直なまでのブラックメタル絵巻を展開してきたように思う。同じカスカディアンというジャンルに属するミネソタ州のPanopticonが「Kentucky」で大胆にバンジョーを取り入れたときは衝撃だったが(私はこのアルバムが非常に好きだ。)、実はWolves in the Throne Roomはそこまで柔軟にジャンルをまたいでいなかった。今作「Thrice Woven」ではさすがにバンジョーやその他の楽器を取り入れることはないものの、今までの彼らからするとかなり新しい要素を取り入れていると思う。女性ボーカルや複雑な構成という強靭な縦糸に、フォークの要素、シンセサイザーの浮遊感、アンビエントパートなどの横糸を噛まして、強靭かつ今までにない色彩豊かな織物を描き出した。それが今作だ。
ある意味相当アヴァンギャルドだった前作がマンネリからの脱却や、第一人者としての重圧からの逃げを打った失敗作とするのではなく、自分たちの本質がどこにあり、どこまで行けるか、ということを確かめる作品だったとすると、全くバンドサウンドを用いないという「Celestite」という作品を経て、改めてブラックメタルの形に回帰し、そしてその幅を大胆不敵に広げてきたのが今作「Thrice Woven」ではと思う。
複雑なバンドだが、私はやはりメロディの残滓の上を紙を引き裂くようなイヴィルなボーカルが疾駆する、ストレートなパートがWolves in the Throne Roomの醍醐味だと思うので(そういった意味ではEP「Malevolent Grain」はすごーく好きな音源。)、今作でもその鋭さが遺憾なく発揮されているのが嬉しい。やはり芯はぶれていない。普通のブラックメタルなら「冬は死につつある、太陽が戻ってきている」と春を称える歌を歌わない。これはやはり野菜を育て豊かな春の訪れの本当の豊穣さ、ありがたみを知っている人でなくてはつくりだせないだろう。崇高な何かに対する畏怖と畏敬の念が詰まっているように思う。そういった意味ではやはり、温かい、血の通ったブラックメタル、という稀有な音楽だ。
ひたすら風格を見せつける最新作。前作に否定的な感想を持った人にこそ聞いてほしいと思う。非常に格好良い。おすすめ。
2017年にArtemisia Recordsからリリースされた。
1stアルバム「Diadem of 12 Stars」を2006年にリリースするやカスカディアン・ブラックメタルというジャンルを圧倒今に打ち立てたブラックメタルバンド。カスカディアンといえば複雑な大作指向でまごうことなきアンダーグランドなジャンルだったが、アトモスフェリックな音作りはその後のブラックメタルとシューゲイザーの融合に影響を与えたのではと密かに思っている。2014年に発表された前作「Celestite」では前編ほぼシンセサイザーの音で構成された内容でファンの度肝を抜いた(おおよそネガティブな方に)バンドの3年ぶりの新作。もしやまた…というファンの不安を裏切り結論から言うと元の完全なブラックメタルなバンドサウンドに回帰している。中心となるのはNathanとAronのWeaver兄弟で、そこにKody Keyworthというメンバーが新しくギターと歌で参加している三人体制。プロデューサーにRundall Dunnを迎え自前のスタジオ(文字通り自分たちで建てたらしい。)で録音された。今でも多分そうだがWeaver兄弟はオーガニックな思想を持ち、そこに根ざすスタンスで活動している。農場で暮らし、電気を使うことに矛盾を感じつつ、ブラックメタルをやっている。
今作「Thrice Woven」は直訳すると「三回織」になる。おそらく織物の形式の一つではと思うが。バンド三人に加えてスウェーデンのシンガーAnna von Hausswolff、それから暗黒メタル界の巨人NeurosisのSteve von Tilがゲストとして参加している。
全5曲で42分。インタールード的な4曲目を除くとだいたい1曲あたり10分くらいだろうか。過去にはもっと長い曲があったが、「Celestial Lineage」から割りと(それまでに比べると)コンパクトに曲を纏める、という動きがあるように思う。そういった意味でも前前作を踏襲する流れなのだが、一通り何回か聞いた後に思うのはやはり問題作となった前作「Celestite」の影響はまだあるなと。確か前作の感想を書いた際に表現の際にブラックメタルという”やり方”がじゃまになったため、というかそのやり方だと表現しきれないため、ああいった別のアプローチを取ったのでは、と書いた。今作でもシンセサイザーは使われているが私が言いたいのはただ今作もシンセサイザーを使っているので、とか微妙にそういうことではなくて。まず今作を聞いて思ったのは曲に今までにない広がりがあることだ。大作指向だし大胆に女性ボーカルをゲストに招いたりしているが、実はこのバンド表現の幅は結構かっちりしている。どちらかと言うと多彩なのは展開であって、あくまでも愚直なまでのブラックメタル絵巻を展開してきたように思う。同じカスカディアンというジャンルに属するミネソタ州のPanopticonが「Kentucky」で大胆にバンジョーを取り入れたときは衝撃だったが(私はこのアルバムが非常に好きだ。)、実はWolves in the Throne Roomはそこまで柔軟にジャンルをまたいでいなかった。今作「Thrice Woven」ではさすがにバンジョーやその他の楽器を取り入れることはないものの、今までの彼らからするとかなり新しい要素を取り入れていると思う。女性ボーカルや複雑な構成という強靭な縦糸に、フォークの要素、シンセサイザーの浮遊感、アンビエントパートなどの横糸を噛まして、強靭かつ今までにない色彩豊かな織物を描き出した。それが今作だ。
ある意味相当アヴァンギャルドだった前作がマンネリからの脱却や、第一人者としての重圧からの逃げを打った失敗作とするのではなく、自分たちの本質がどこにあり、どこまで行けるか、ということを確かめる作品だったとすると、全くバンドサウンドを用いないという「Celestite」という作品を経て、改めてブラックメタルの形に回帰し、そしてその幅を大胆不敵に広げてきたのが今作「Thrice Woven」ではと思う。
複雑なバンドだが、私はやはりメロディの残滓の上を紙を引き裂くようなイヴィルなボーカルが疾駆する、ストレートなパートがWolves in the Throne Roomの醍醐味だと思うので(そういった意味ではEP「Malevolent Grain」はすごーく好きな音源。)、今作でもその鋭さが遺憾なく発揮されているのが嬉しい。やはり芯はぶれていない。普通のブラックメタルなら「冬は死につつある、太陽が戻ってきている」と春を称える歌を歌わない。これはやはり野菜を育て豊かな春の訪れの本当の豊穣さ、ありがたみを知っている人でなくてはつくりだせないだろう。崇高な何かに対する畏怖と畏敬の念が詰まっているように思う。そういった意味ではやはり、温かい、血の通ったブラックメタル、という稀有な音楽だ。
ひたすら風格を見せつける最新作。前作に否定的な感想を持った人にこそ聞いてほしいと思う。非常に格好良い。おすすめ。
2017年11月19日日曜日
Iron Monkey/9-13
イギリスはイングランド、ノッティンガムのスラッジコアバンドの3rdアルバム。
2017年にRelapse Recordsからリリースされた。
Iron Monkeyは1994年に結成されたバンド。Earacheから2枚のオリジナルアルバムと日本のChurch of Miseryとのスプリットなど幾つかの音源をリリースして後、1999年に解散。その後2002年にはボーカル担当のJohnny Morrowが心臓発作により逝去。Iron Monkeyといえばこのボーカル、ってこともあり再結成は絶望的に。ところが今年になって再結成して作った音源がこちら。ギターを弾いていたオリジナルメンバーJim Rushbyが真っ白い覆面マスクをかぶってボーカルを担当(ギターも弾く)。解散前に脱退したギタリストであるSteve Watsonがベースに転向。ドラムにScott Briggsを迎えた三人編成。Briggsはアーティスト写真でただならぬ存在感を漂わせているな…と思ったらハードコアパンクバンドChaos U.K.のドラマーとのこと。ボーカル不在という難しい状況をオリジナルメンバーを主体に再結成ということでこれはかなり期待が煽られるというもの。私はだいぶ遅れてオリジナルアルバム2枚セットの音源を買った周回遅れの後追いで、多分それが起因して今回の音源は結論から言うと非常に楽しめています。(オリジナルのボーカリストの魅力が…という意見もあるようで、やはり思い入れのある方はそういう感想を持ってしまうこともあるよなと。私も当時から聴いていたら多分そうだったと思う。)
イギリスと言うと紳士の国だが、ドゥームの国でもあるというのは半ば常識であって、そもそもからBlack Sabbathがイングランド出身ということもあり、現行ではやはりElectric Wizardや解散してしまったけどCathedral(とRise Above Records)などなど、激しいだけでなく怪しい、不穏である、剣呑な、退廃的な、そんな形容詞のよく似合うドゥームバンドをたくさん排出しております。私は激しさの探求からスラッジコアにたどり着いてやはりEyehategod(アメリカ、ニューオーリンズのバンド)を聴いてわかりやすく「やべー」となった口。Iron Monkeyを聴いたときはその一見するとの聞きやすさにびっくりしたものの、すぐにその軽快かつだるくて不穏な音世界にハマったものだ。
音質的には確実に2010年台の洗練されて迫力のある音にアップデートされている。ジリジリした感じは消えて非常にクリアだ。ただ中身的にはやはりIron Monkeyだ。バンドが存続していたらなるほどこういう音を出していただろうと言う感じ。スラッジコア/サイケ・ドゥームを自称することもあってただただ遅く陰惨なスラッジとは一線を画す音と曲作り。ヴィンテージ感のあるロックからの由来を感じさせる溜めのある、ひっぱるようなリフが特徴でゴリゴリ圧殺系とは明らかに異なるうねりのあるリズム感が魅力。決して音の数は多くないのに魔術のような空間を組み立てるリフ。もっと危険な音を出すバンドはあるが、このIron Monkeyの現実的なヤバさというのはジャンルは異なるがUNSANEなんかに似ているかも。ひょっとしたらストリート感と言っても良いかもしれない。不敵に微笑む危険な男、という感じで余裕がある感じが逆に不穏だ。酩酊しきって酔歩するように経過なロック/ドゥームの境界を超えて、明らかに行き過ぎた/やりすぎた感のあるスラッジの世界に足を突っ込むところが最高。前半のノリの良さがゲートウェイでヤバみが増してくる後半に気づくと案内されている、というかケツを足蹴にされて悪夢の陥穽に落ちたような非道な感じ。ラスト「Moreland St.Hammervortex」は大団円という感じ。
そしてやはりボーカルが一番気になるところ。なくなったJohnny Morrowという人はほんとう危険な感じのする声の持ち主で混沌とした悪徳を声で表現した、みたいな魅力の持ち主だった。このバンドの(当時の)看板はMorrowの独特なボーカリゼーションということは残されたメンバーも自覚するところであって、全く異なる系統のボーカルを載せるというよりはMorrowの歌唱法をなぞるようにJimがマイクを取る。前のボーカリストは上手い下手とかではない次元で人を魅了したが、その魅力は声質によるところもあって、異常なしゃがれ声だった。さすがにJimは体格と喉も別物なのでそのしゃがれの妙味というのはほぼない。ただぐしゃっと潰したようなこもった高音がよく出た耳障りな下品な、というところはかなり良い味を出している。ナチュラルに歌い上げる、もしくは叫ぶ(Morrowはかなりナチュラルに思える。)というよりはやはり演技力というのは明らかに酷だけど装飾性を感じるのは確か。ただし個人的にはこのくらいくどい方がいかがわしさがあって良いと思う。私的にはIron Monkeyの今のボーカルはJimで全く問題ない。思い入れのある方はまた違うのだろうが。
Iron Monkeyは名前だけしか知らないな〜という人はまずこの音源から買ってみたら時代のギャップはないと思う。Iron MonkeyといえばJohnny Morrowでしょ!という人も気持ちはわかるが、一旦通して聴いてほしい。やはり他に類を見ないバランスの”悪い”スラッジコアを鳴らすバンドだと思う。
どうでもいいけどとにかくあのお猿のロゴが格好良すぎてパーカーとLPのバンドルを買った上にT-シャツも購入した。もったいなくて着れないくらいかっこいい。
2017年にRelapse Recordsからリリースされた。
Iron Monkeyは1994年に結成されたバンド。Earacheから2枚のオリジナルアルバムと日本のChurch of Miseryとのスプリットなど幾つかの音源をリリースして後、1999年に解散。その後2002年にはボーカル担当のJohnny Morrowが心臓発作により逝去。Iron Monkeyといえばこのボーカル、ってこともあり再結成は絶望的に。ところが今年になって再結成して作った音源がこちら。ギターを弾いていたオリジナルメンバーJim Rushbyが真っ白い覆面マスクをかぶってボーカルを担当(ギターも弾く)。解散前に脱退したギタリストであるSteve Watsonがベースに転向。ドラムにScott Briggsを迎えた三人編成。Briggsはアーティスト写真でただならぬ存在感を漂わせているな…と思ったらハードコアパンクバンドChaos U.K.のドラマーとのこと。ボーカル不在という難しい状況をオリジナルメンバーを主体に再結成ということでこれはかなり期待が煽られるというもの。私はだいぶ遅れてオリジナルアルバム2枚セットの音源を買った周回遅れの後追いで、多分それが起因して今回の音源は結論から言うと非常に楽しめています。(オリジナルのボーカリストの魅力が…という意見もあるようで、やはり思い入れのある方はそういう感想を持ってしまうこともあるよなと。私も当時から聴いていたら多分そうだったと思う。)
イギリスと言うと紳士の国だが、ドゥームの国でもあるというのは半ば常識であって、そもそもからBlack Sabbathがイングランド出身ということもあり、現行ではやはりElectric Wizardや解散してしまったけどCathedral(とRise Above Records)などなど、激しいだけでなく怪しい、不穏である、剣呑な、退廃的な、そんな形容詞のよく似合うドゥームバンドをたくさん排出しております。私は激しさの探求からスラッジコアにたどり着いてやはりEyehategod(アメリカ、ニューオーリンズのバンド)を聴いてわかりやすく「やべー」となった口。Iron Monkeyを聴いたときはその一見するとの聞きやすさにびっくりしたものの、すぐにその軽快かつだるくて不穏な音世界にハマったものだ。
音質的には確実に2010年台の洗練されて迫力のある音にアップデートされている。ジリジリした感じは消えて非常にクリアだ。ただ中身的にはやはりIron Monkeyだ。バンドが存続していたらなるほどこういう音を出していただろうと言う感じ。スラッジコア/サイケ・ドゥームを自称することもあってただただ遅く陰惨なスラッジとは一線を画す音と曲作り。ヴィンテージ感のあるロックからの由来を感じさせる溜めのある、ひっぱるようなリフが特徴でゴリゴリ圧殺系とは明らかに異なるうねりのあるリズム感が魅力。決して音の数は多くないのに魔術のような空間を組み立てるリフ。もっと危険な音を出すバンドはあるが、このIron Monkeyの現実的なヤバさというのはジャンルは異なるがUNSANEなんかに似ているかも。ひょっとしたらストリート感と言っても良いかもしれない。不敵に微笑む危険な男、という感じで余裕がある感じが逆に不穏だ。酩酊しきって酔歩するように経過なロック/ドゥームの境界を超えて、明らかに行き過ぎた/やりすぎた感のあるスラッジの世界に足を突っ込むところが最高。前半のノリの良さがゲートウェイでヤバみが増してくる後半に気づくと案内されている、というかケツを足蹴にされて悪夢の陥穽に落ちたような非道な感じ。ラスト「Moreland St.Hammervortex」は大団円という感じ。
そしてやはりボーカルが一番気になるところ。なくなったJohnny Morrowという人はほんとう危険な感じのする声の持ち主で混沌とした悪徳を声で表現した、みたいな魅力の持ち主だった。このバンドの(当時の)看板はMorrowの独特なボーカリゼーションということは残されたメンバーも自覚するところであって、全く異なる系統のボーカルを載せるというよりはMorrowの歌唱法をなぞるようにJimがマイクを取る。前のボーカリストは上手い下手とかではない次元で人を魅了したが、その魅力は声質によるところもあって、異常なしゃがれ声だった。さすがにJimは体格と喉も別物なのでそのしゃがれの妙味というのはほぼない。ただぐしゃっと潰したようなこもった高音がよく出た耳障りな下品な、というところはかなり良い味を出している。ナチュラルに歌い上げる、もしくは叫ぶ(Morrowはかなりナチュラルに思える。)というよりはやはり演技力というのは明らかに酷だけど装飾性を感じるのは確か。ただし個人的にはこのくらいくどい方がいかがわしさがあって良いと思う。私的にはIron Monkeyの今のボーカルはJimで全く問題ない。思い入れのある方はまた違うのだろうが。
Iron Monkeyは名前だけしか知らないな〜という人はまずこの音源から買ってみたら時代のギャップはないと思う。Iron MonkeyといえばJohnny Morrowでしょ!という人も気持ちはわかるが、一旦通して聴いてほしい。やはり他に類を見ないバランスの”悪い”スラッジコアを鳴らすバンドだと思う。
どうでもいいけどとにかくあのお猿のロゴが格好良すぎてパーカーとLPのバンドルを買った上にT-シャツも購入した。もったいなくて着れないくらいかっこいい。
DS-13/UMEÅ HARDCORE FOREVER, FOREVER UMEÅ HARDCORE
スウェーデンはヴェステルボッテン県(調べるとスウェーデンの上の方)、ウメオのハードコアバンドのディスコグラフィー盤。
2017年にLPやCDの形式で複数のレーベルからリリースされた。私が買ったのは日本のCrew for Life Recordsからリリースされた日本盤。(CD形式は日本盤だけみたい。)
DS-13はDemon System 13の意味で1996年に結成、本国だけでなくアメリカ、ヨーロッパ、日本なども含めて世界的に活動したが2002年に一度解散。2012年に再結成し、また精力的に活動している。Pusheadのイラストを使った音源は聞いたことない私でもなんとなーく知っていた。おそらく来日を記念してという意味もあってのこのディスコグラフィー日本盤だろうと思う。私は再来日ライブには行けなかった。この音源とても内容が素晴らしいので非常に残念。
この音源はアルバムを除く1997年から2000年までのスプリット音源や、EP、コンピレーションに収録、提供した音源を集めたもの。全部で67曲あり、リマスターが施されている。
最近日本のハードコアバンドのインタビューを読むと一昔前は本当にハードコアを聞く人が少なくて大変だったようだ。最近は(自分が興味を持ったことも大きいだろうけど)一昔前に比べるとやや盛り上がってきたのかな?という感じ。
このDS-13は1996年から活動しているバンドだから現行スタイルにはむしろ影響を与えた方のバンド。67曲を聞いてて思ったのは非常に聞きやすいってこと。(とくにパワーバイオレンスなどの激しいタイプの)ハードコアバンドは1曲が短いからアルバム全体も短くなる傾向にある。短くても中身的には結構重たくて濃いので、濃厚な家系ラーメンのように短い尺がちょうどよいくらいなのだけど、このバンドに関しては67曲がすっと聴ける!それもあとに残らない軽さではなく、これはいい曲、これもいい曲という感じに耳を通して脳にガツガツくる。こういうのはなかなかない。ディスコグラフィーだから良い曲のみを集めたベスト盤ってわけでもないし。この聞きやすさの秘密は今のところ3つくらいあって、一つは音がおもたすぎないこと。低音をバリバリ強調して不穏でノイジーなフィードバックノイズを添えた昨今の音とは一線を画す、ハードコアパンクの延長線上にある中音域の厚みがあたたかみすらある音が非常に気持がよい。もう一つは曲によって聞き所がきちんと用意されていること。たしかにとんでもない速度で突っ走る曲がほとんどなのだが、スラッシュ一辺倒でなくて結構コード感のある聞きやすいパンクな曲構成になっていたりもする。シンガロングに彩られたメロディが出て来る曲もある。(「Degenerated Generation」や「(I'm Not Your)Steppin' Stone」なんかは歌えるくらいキャッチー。)強烈な速度とその極端にある急停止からの鈍足、というスタイルが(もちろん良いことでもある)一つのやり方になっている昨今は特に、こういうふうに脇道にそれているというか、いろいろな試行錯誤が、結果的に勢いのある曲を主体とした音源の中でいい感じに異彩をはなちつつ凹凸を作っている。そして最後の要素は全体を覆うポジティブ感。ぬるいポップパンクだというのではないし「死んだ警官だけが良い警官だ!」と叫ぶ過激さ、攻撃性がありながらも、音的には陰惨にならないでエネルギッシュでありながら創造的だ。聴いていて単純に元気が出てくる。
演奏の感じやボーカルの親しみやすさからCharles Bronsonにちょっとだけ似ているかな?なんて思った。非常に格好良くこのDS-13というバンドを紹介しているディスコグラフィーだと思う。現行のパワーバイオレンスのようなキレッキレのハードコアが好きな人も、きっちりとしたハードコアパンクが好きなのだという人にも進められる音源では…なんて思ったりする。非常におすすめ。
2017年にLPやCDの形式で複数のレーベルからリリースされた。私が買ったのは日本のCrew for Life Recordsからリリースされた日本盤。(CD形式は日本盤だけみたい。)
DS-13はDemon System 13の意味で1996年に結成、本国だけでなくアメリカ、ヨーロッパ、日本なども含めて世界的に活動したが2002年に一度解散。2012年に再結成し、また精力的に活動している。Pusheadのイラストを使った音源は聞いたことない私でもなんとなーく知っていた。おそらく来日を記念してという意味もあってのこのディスコグラフィー日本盤だろうと思う。私は再来日ライブには行けなかった。この音源とても内容が素晴らしいので非常に残念。
この音源はアルバムを除く1997年から2000年までのスプリット音源や、EP、コンピレーションに収録、提供した音源を集めたもの。全部で67曲あり、リマスターが施されている。
最近日本のハードコアバンドのインタビューを読むと一昔前は本当にハードコアを聞く人が少なくて大変だったようだ。最近は(自分が興味を持ったことも大きいだろうけど)一昔前に比べるとやや盛り上がってきたのかな?という感じ。
このDS-13は1996年から活動しているバンドだから現行スタイルにはむしろ影響を与えた方のバンド。67曲を聞いてて思ったのは非常に聞きやすいってこと。(とくにパワーバイオレンスなどの激しいタイプの)ハードコアバンドは1曲が短いからアルバム全体も短くなる傾向にある。短くても中身的には結構重たくて濃いので、濃厚な家系ラーメンのように短い尺がちょうどよいくらいなのだけど、このバンドに関しては67曲がすっと聴ける!それもあとに残らない軽さではなく、これはいい曲、これもいい曲という感じに耳を通して脳にガツガツくる。こういうのはなかなかない。ディスコグラフィーだから良い曲のみを集めたベスト盤ってわけでもないし。この聞きやすさの秘密は今のところ3つくらいあって、一つは音がおもたすぎないこと。低音をバリバリ強調して不穏でノイジーなフィードバックノイズを添えた昨今の音とは一線を画す、ハードコアパンクの延長線上にある中音域の厚みがあたたかみすらある音が非常に気持がよい。もう一つは曲によって聞き所がきちんと用意されていること。たしかにとんでもない速度で突っ走る曲がほとんどなのだが、スラッシュ一辺倒でなくて結構コード感のある聞きやすいパンクな曲構成になっていたりもする。シンガロングに彩られたメロディが出て来る曲もある。(「Degenerated Generation」や「(I'm Not Your)Steppin' Stone」なんかは歌えるくらいキャッチー。)強烈な速度とその極端にある急停止からの鈍足、というスタイルが(もちろん良いことでもある)一つのやり方になっている昨今は特に、こういうふうに脇道にそれているというか、いろいろな試行錯誤が、結果的に勢いのある曲を主体とした音源の中でいい感じに異彩をはなちつつ凹凸を作っている。そして最後の要素は全体を覆うポジティブ感。ぬるいポップパンクだというのではないし「死んだ警官だけが良い警官だ!」と叫ぶ過激さ、攻撃性がありながらも、音的には陰惨にならないでエネルギッシュでありながら創造的だ。聴いていて単純に元気が出てくる。
演奏の感じやボーカルの親しみやすさからCharles Bronsonにちょっとだけ似ているかな?なんて思った。非常に格好良くこのDS-13というバンドを紹介しているディスコグラフィーだと思う。現行のパワーバイオレンスのようなキレッキレのハードコアが好きな人も、きっちりとしたハードコアパンクが好きなのだという人にも進められる音源では…なんて思ったりする。非常におすすめ。
ダン・シモンズ/エンディミオン
アメリカの作家のSF小説。
「ハイペリオン」シリーズの第3弾。順調に読み進めてまいりました。
上巻は新品で買えたのだが、下巻が品切れて中古で購入。
7人の巡礼たちの物語が終わって300年。人類はテクノコアと決別し、瞬間転移などテクノコア由来の技術の多くが使用できなくなり、人類の統合組織は崩壊。恒星間の距離が再び絶対的なものになり、移動に時間が掛かる分各惑星は断絶状態になり、独自の進歩を続けていくことになった。そんな第二期の宇宙史でヘゲモニー時代は虫の息だったカトリック教会がテクノコアの技術、人体を組成させる十字架の改良に成功。蘇生の際の人体劣化を克服し、人類にほぼ完全な不死を提供することであっという間に宇宙における人類の領域を征服していく。巡礼たちの物語も過去の伝説めいたものになりつつある”今”、伝説の舞台になった惑星ハイペリオンに生まれたロール・エンディミオンはなんとなく気に入らない、という理由からカトリックの洗礼(つまり不死)を拒否。自由気ままに暮らしていたが、ある日冤罪で死刑の憂き目に合うことに。窮地の彼を救ったのは伝説の巡礼のうち一人、「詩篇」を書いたマーティン・サイリーナスだった。彼はロールに対して人類の救世主となる巡礼の一人の子供である少女を守って銀河を救えという。
「ハイペリオン」シリーズは全部で4つの物語があるが(文庫だと全部上下分冊だから全部で8冊。)、一旦前作「ハイペリオンの没落」で物語的には一区切り。登場人物や設定は引き継ぎつつ、大きなブレイクスルー(人類の不死の獲得)と時間の経過(300年)を間にはさみつつ、また新しい物語がこの「エンディミオン」と続く「エンディミオンの覚醒」で書かれることになる。
読んでみると前作までとは色々変わっていて面白い。まず設定だけど転移ゲートがもたらす、瞬間転移技術(これはその仕組は人類は結局わからなかったけど便利だから使い続けていた、という設定が人類らしく適当で良い。)がなくなったこともあり、人類同士の連携が取れずに宇宙にいながら文明は大きく後退している。技術の間断ない共有というのが進歩に大きく有効であるということがよく分かる。前作ではヘゲモニーという組織が人類の音頭を取っていたが、これが崩壊し、とっくに捨て去ったはずの神権政治が取って代わっている。それも不死をちらつかせての反映だから(ココらへんにも人間の弱さ、都合の善さが表現されている)、実際ろくなもんでもないことははじめからわかっている。前作ではつましい求道者だったキリスト教徒は醜い権力者になっている。
それから物語の構造も変わっていて、過去の因縁がある7人の巡礼が集まり、過去を語りながら宇宙の欺瞞を暴きつつ、その後の世界を変える戦いに結実した重たい(もちろん褒め言葉で)前二作に比較すると、今回新しい主人公は良くも悪くも軽い男で重たい過去も因縁もなく、いわば巻き込まれ型と言うかたちで物語に参加することになる。小さい女の子と給仕のようなアンドロイド(彼は典型的な執事キャラで肌は真っ青という物語的な個性がある。スターウォーズにも通じる典型的な感じがある。)と悪い奴ら、つまりカトリック教会からただひたすら逃げていく、というシンプルな物語になっている。これによって娯楽性が大いにましており、あとがきにも書かれているとおり本当にただただ若者二人+アンドロイドの逃避行、ってことになっている。物語の面白さはその構造的な複雑さや逆に単純さにはよらない、というのは非常に面白い。逃避行は惑星巡り、と言うかたちになっており、全く道の新世界という要素と、現代のつまり読む人がいる今の世界に通じる基地の要素がうまく混ぜ合わさり、地球とは異なる環境(その中の幾つかは非常に極端、つまりすごく寒いとか、呼吸ができないとか)で再現されている。この物語はなんといってもこの異星、異世界といっていいほどの魅力がある別世界の描写が素晴らしい。想像力の限界に挑む、という新奇さだけでなくなんとなくノスタルジックな現代の残り香があるところがその魅力の秘密かと思う。
敵を張るカトリック教会サイドのキャラクターも魅力的で(ただし一部不満もあってそれは今読んでいる「エンディミオンの覚醒」の時に書くと思う。)物語を盛り上げる。
どうやら4部作でこの物語が一番好きだという人もいるらしい。多分前二作を読まなくてもわかると思うけど、可能だったらやはり「ハイペリオン」から読んだほうが良いと思う。
2017年11月5日日曜日
V.A./Twin Peaks:Music From The Limited Event Series
アメリカのTVドラマのサウンドトラック。
2017年にRhino Entertainment Company、a Warner Music Group Companyからリリースされた。
今年ハマったものがあってそれがアメリカのTVドラマ「Twin Peaks」。鬼才デヴィッド・リンチがマーク・フロストとタッグを組んで作成したドラマで1990年に放送開始され、その後日本でもブームになった。私はたしか秋本治さんの漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」でその名前が出てきたのを覚えているが、当時ドラマは見たことがなかった。今年25年ぶりに新作「Twin Peaks The Return」が放送されるということで、「へー」くらいに思っていたが私の上司が「Twin Peaks」のファンで「見れるなら絶対見ろ!」ってことなので(「Twin Peaks」はいまんとこwowowでしか見れない状態で私の家はwowowが見れる。)、新シーズン前に放送された旧シリーズを見たらこれがまたすごい面白いくてどっぷりハマったわけ。
新シリーズは面白いことにエンディングの曲が毎回異なる。劇中でロードハウスと呼ばれるバー(正式名称はバンバンバー(Bang Bang Bar))で様々なアーティストがライブを披露する、という体裁でエンディング曲が流れるのだ。(これ子供の頃に例えば自分アニメとかの監督になったら毎回好きな曲流したいな!とか誰でも妄想すると思う。)その曲がいちいち格好いいので個別に買うよりは、と思ってそのエンディング曲を集めたサウンドトラックを購入したわけ。(別に劇中の曲を収録したサントラもある。)
なんといっても目玉は第8話にでてくるnine inch nailsの「She's Gone Away」かな。曲自体はもうバンドの「Not Actual Events」というEPで聴いていたのだが、なんとこの曲はリンチの要望でこのドラマのために描き下ろしたものとは知らなかったな。しかも一回作ったものをリンチが「明るいな〜、こういうのじゃないんだよな〜」ってボツにしたんだって。ninに曲作ってもらったらどんな曲でも「すげー曲っす!もちOKす!!」って普通はなると思うのだけど、さすが監督すげーなと思います。
「Twin Peaks」はとある少女の殺害事件から端を発する、冒頭はわりとかっちりした犯罪捜査者かなと思いきや、回を重ねるごとに怪しい世界に入り込んでいく作品。リンチ監督も御年70歳を超えてくるということでもっとおとなしめの、ぼやーっとした曲が多いのかと思いきやninもそうだけどかなりしっかりとした、多彩な曲が並んでいるのが印象的。びく皆曲もあるけど、明るい曲も多い。やはりアメリカということでカントリー調の曲もそれなりにある。「Twin Peaks」はただ殺人を、ただ不気味さを書いている作品ではなくて、ワシントン州にある架空の小さい町ツイン・ピークスとその子に住む様々な人々の生活の模様を書いている作品である。ロードハウスというのはそんなツイン・ピークスに住む人がやすらぎや、楽しみを求めに来る場所なので当然、架空の登場人物、主人公たちだけでなく街に住む普通の人々が好んで毎日聞きそうな曲が選ばれているのだと思う。恐れる曲もあれば、しっとり聞ける曲もあるが、通して聴いてみるとどれも没入感のある、かなり力のこもった曲ばかり選ばれているように思う。安易に日本のテレビ番組を批判するのもちょっとどうかと思うが、例えば主役を張るアイドルの男の子、女の子が所属する、とにかくポップで名だたるプロデューサーが手がけたよくも悪くも軽い曲、というのとは一線を画す内容でどれも非常に重たく、濃い。毎日がただ良いことの連続で内容に、架空の、存在すらしない人々の気持ちを反映したかのような豊かな感情が、バリエーションの有る楽曲に現れているのだと思う。ドラマを見ていない人がこのアルバムを聞いてどう思うのかは気になるところだけど、ドラマを見ると最後の曲が毎回違う、曲の雰囲気も輪ごとにガラリと変わるというのは「Twin Peaks The Return」の場合は非常にしっくり来る。見た人ならわかるだろうがリンチ監督は尺を贅沢に、普通の監督なら省くような人の動きをゆっくり、じっくり、執拗に時間をかけて画面に映し出す。そこには喜怒哀楽というシンプルな4つの元素に分解できない何かに対する強いこだわりがある。それ故何が言いたいのかわかりにくいと批判されることもあるだろう。ちなみにデヴィッド・リンチは音楽に対して非常にこだわりのある人でたしか自分でも作曲をするはずだ。そんな監督のこだわりが選曲にも表れているなと。
個人的に気に入ったのはどっしりとしたラテンのリズムに半端ない声量と技量がのっかるRebekah Del Rioの「No Stars」。重厚なのに歌いたくなるくらいポップなのがすげー。ひたすらクールなロックンロールZZ Topの「Sharp Dressed Man」。むかし車のCMとかで目にしたZZ TOP初めて聴いた。声がすごくセクシー。アメリカ!のイメージをそのまま曲にしたような爽快さ。
「Twin Peaks」はとても面白いドラマなので是非オススメしたいが、やはり新旧合わせるとそれなりにボリュームがあるので躊躇する人もいるだろう。まずはサントラ聴いて雰囲気を掴んでは、ってのは難しいか。私は本編に好感があるからそれがサントラにも反映されていると思うが、それを抜きにしても良いアルバムだと思うので気になった人は是非どうぞ。
ninが出た8話放送時はやっぱり興奮した!
2017年にRhino Entertainment Company、a Warner Music Group Companyからリリースされた。
今年ハマったものがあってそれがアメリカのTVドラマ「Twin Peaks」。鬼才デヴィッド・リンチがマーク・フロストとタッグを組んで作成したドラマで1990年に放送開始され、その後日本でもブームになった。私はたしか秋本治さんの漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」でその名前が出てきたのを覚えているが、当時ドラマは見たことがなかった。今年25年ぶりに新作「Twin Peaks The Return」が放送されるということで、「へー」くらいに思っていたが私の上司が「Twin Peaks」のファンで「見れるなら絶対見ろ!」ってことなので(「Twin Peaks」はいまんとこwowowでしか見れない状態で私の家はwowowが見れる。)、新シーズン前に放送された旧シリーズを見たらこれがまたすごい面白いくてどっぷりハマったわけ。
新シリーズは面白いことにエンディングの曲が毎回異なる。劇中でロードハウスと呼ばれるバー(正式名称はバンバンバー(Bang Bang Bar))で様々なアーティストがライブを披露する、という体裁でエンディング曲が流れるのだ。(これ子供の頃に例えば自分アニメとかの監督になったら毎回好きな曲流したいな!とか誰でも妄想すると思う。)その曲がいちいち格好いいので個別に買うよりは、と思ってそのエンディング曲を集めたサウンドトラックを購入したわけ。(別に劇中の曲を収録したサントラもある。)
なんといっても目玉は第8話にでてくるnine inch nailsの「She's Gone Away」かな。曲自体はもうバンドの「Not Actual Events」というEPで聴いていたのだが、なんとこの曲はリンチの要望でこのドラマのために描き下ろしたものとは知らなかったな。しかも一回作ったものをリンチが「明るいな〜、こういうのじゃないんだよな〜」ってボツにしたんだって。ninに曲作ってもらったらどんな曲でも「すげー曲っす!もちOKす!!」って普通はなると思うのだけど、さすが監督すげーなと思います。
「Twin Peaks」はとある少女の殺害事件から端を発する、冒頭はわりとかっちりした犯罪捜査者かなと思いきや、回を重ねるごとに怪しい世界に入り込んでいく作品。リンチ監督も御年70歳を超えてくるということでもっとおとなしめの、ぼやーっとした曲が多いのかと思いきやninもそうだけどかなりしっかりとした、多彩な曲が並んでいるのが印象的。びく皆曲もあるけど、明るい曲も多い。やはりアメリカということでカントリー調の曲もそれなりにある。「Twin Peaks」はただ殺人を、ただ不気味さを書いている作品ではなくて、ワシントン州にある架空の小さい町ツイン・ピークスとその子に住む様々な人々の生活の模様を書いている作品である。ロードハウスというのはそんなツイン・ピークスに住む人がやすらぎや、楽しみを求めに来る場所なので当然、架空の登場人物、主人公たちだけでなく街に住む普通の人々が好んで毎日聞きそうな曲が選ばれているのだと思う。恐れる曲もあれば、しっとり聞ける曲もあるが、通して聴いてみるとどれも没入感のある、かなり力のこもった曲ばかり選ばれているように思う。安易に日本のテレビ番組を批判するのもちょっとどうかと思うが、例えば主役を張るアイドルの男の子、女の子が所属する、とにかくポップで名だたるプロデューサーが手がけたよくも悪くも軽い曲、というのとは一線を画す内容でどれも非常に重たく、濃い。毎日がただ良いことの連続で内容に、架空の、存在すらしない人々の気持ちを反映したかのような豊かな感情が、バリエーションの有る楽曲に現れているのだと思う。ドラマを見ていない人がこのアルバムを聞いてどう思うのかは気になるところだけど、ドラマを見ると最後の曲が毎回違う、曲の雰囲気も輪ごとにガラリと変わるというのは「Twin Peaks The Return」の場合は非常にしっくり来る。見た人ならわかるだろうがリンチ監督は尺を贅沢に、普通の監督なら省くような人の動きをゆっくり、じっくり、執拗に時間をかけて画面に映し出す。そこには喜怒哀楽というシンプルな4つの元素に分解できない何かに対する強いこだわりがある。それ故何が言いたいのかわかりにくいと批判されることもあるだろう。ちなみにデヴィッド・リンチは音楽に対して非常にこだわりのある人でたしか自分でも作曲をするはずだ。そんな監督のこだわりが選曲にも表れているなと。
個人的に気に入ったのはどっしりとしたラテンのリズムに半端ない声量と技量がのっかるRebekah Del Rioの「No Stars」。重厚なのに歌いたくなるくらいポップなのがすげー。ひたすらクールなロックンロールZZ Topの「Sharp Dressed Man」。むかし車のCMとかで目にしたZZ TOP初めて聴いた。声がすごくセクシー。アメリカ!のイメージをそのまま曲にしたような爽快さ。
「Twin Peaks」はとても面白いドラマなので是非オススメしたいが、やはり新旧合わせるとそれなりにボリュームがあるので躊躇する人もいるだろう。まずはサントラ聴いて雰囲気を掴んでは、ってのは難しいか。私は本編に好感があるからそれがサントラにも反映されていると思うが、それを抜きにしても良いアルバムだと思うので気になった人は是非どうぞ。
ninが出た8話放送時はやっぱり興奮した!
THE DONOR/ALL BLUES
日本は石川県金沢市のハードコアバンドの2ndアルバム。
2017年にTill Your Death Recordsからリリースされた。
前作「AGONY」からコンピレーションアルバムの参加などを経て3年ぶりにリリースされた新作。真っ黒いイメージが印象的だった前作から打って変わって白を貴重としたアートワークになっている。ギタリストは同じ金沢のGreenMachineでも活動している。このアルバムのアートワークに使われている写真も多分GreenMachineのメンバーが撮ったものだと思う。
全部で10曲を22分で駆け抜けるわけだからだいたいその音楽性はわかると思う。今年リリースされた3LAのコンピレーションにも曲を提供していたが、いわゆるネオクラスト、激情とは一線を画する音楽性。もともと内省的な音楽性を日本の激情バンドたちはさらに激化させた内容にアップデートして悩み苦しむハードコアにしている印象もあるが(批判しているわけではない)、THE DONORはその流れにはあまり与しないようだ。悩みがない人間は私が知っている限り存在しないが、その内省的な葛藤をこのバンドはすべて攻撃力と機動力のパラメータに振り切っているようだ。多分に感情的だが、叙情的とはいえない。音楽ジャンルとしてのエモーショナルなハードコアとは距離をおいた荒涼としたハードコアを演奏している。
とにかくささくれだって重量感のある、錆びついた金属のようなギターの音質はたわんだ北欧のメタル/ハードコアを彷彿とさせる。はじめ聞いたときは前作以上に例えばTrap Themのようなバンドの出すサウンドに通じるところがあると思う。速さの逆を行く遅さ、つまりスラッジ成分も取り込んでいるところもその手のハードコアに通じるところがある。いわゆるアンビエント、アトモスフェリック、ポストといった形容詞が表現するともすると冗長、高尚になってしまう要素に関してはこれを余計な夾叉物として一切を排除する。いわば極悪非道なハードコアなのだが、よくよく考えてみるとこういったピュアなバンドというのはなかなか日本にはいないかもしれない。もっと先鋭化してパワーバイオレンスの荒涼とした地平にひたすら残虐性とヘイトを求めるか、もしくは日本人の真面目さを反映した悩み多き鬱屈さを追求するエモバイオレンス方面のハードコアに舵を切るか、その二択のいずれかを選択するようなバンドが多い気がする中、あえてピュアなハードコアを鳴らすというのは結構稀有ではと思う。
ただまったくもって北欧スタイルを金沢で再生したのがTHE DONORかというとそこが少し違くて、そしてそこがこのバンドの面白いところ。激しい音楽に抒情性を混ぜ込む、というのは陳腐な言い回しだが、実際にやるとなるとある程度手法は決まっていて、そういった意味では日本の激情はその手の表現が得意である。THE DONORはここを別の手法で攻めていて、感覚的にはトレモロに感情を込めるブラックメタルに似ているが、そこまでわかり易くないのが、チャレンジンクで面白いし、仕上がりが絶妙に格好いい。そういった意味では3LAのコンピ「ろくろ」に提供した「kagerou」はやはり白眉の出来では。コンピとアルバムでは別バージョンになっており違いを楽しむことができる。とにかくアウトロの放り出すような、ヤケクソめいた表現が曲の終わりってことで最高のクライマックスになっている。
いわゆるジャパニーズスタイルのハードコアが激しい音楽性にいろいろな形で豊かな表現を取り入れたとしたら、やはりこのバンドもその系譜にあるということだろうか。
前作をまっとうにアップデートさせた素晴らしい内容でこの手の音楽が好きなら聞き逃す手はない非常におすすめしたい音源。この音源とそれに伴うライブの後、THE DONORは年内での活動休止をアナウンスしている。非常に残念なことだ。視聴できるところが見つからなかったので買って聴いてください。
2017年にTill Your Death Recordsからリリースされた。
前作「AGONY」からコンピレーションアルバムの参加などを経て3年ぶりにリリースされた新作。真っ黒いイメージが印象的だった前作から打って変わって白を貴重としたアートワークになっている。ギタリストは同じ金沢のGreenMachineでも活動している。このアルバムのアートワークに使われている写真も多分GreenMachineのメンバーが撮ったものだと思う。
全部で10曲を22分で駆け抜けるわけだからだいたいその音楽性はわかると思う。今年リリースされた3LAのコンピレーションにも曲を提供していたが、いわゆるネオクラスト、激情とは一線を画する音楽性。もともと内省的な音楽性を日本の激情バンドたちはさらに激化させた内容にアップデートして悩み苦しむハードコアにしている印象もあるが(批判しているわけではない)、THE DONORはその流れにはあまり与しないようだ。悩みがない人間は私が知っている限り存在しないが、その内省的な葛藤をこのバンドはすべて攻撃力と機動力のパラメータに振り切っているようだ。多分に感情的だが、叙情的とはいえない。音楽ジャンルとしてのエモーショナルなハードコアとは距離をおいた荒涼としたハードコアを演奏している。
とにかくささくれだって重量感のある、錆びついた金属のようなギターの音質はたわんだ北欧のメタル/ハードコアを彷彿とさせる。はじめ聞いたときは前作以上に例えばTrap Themのようなバンドの出すサウンドに通じるところがあると思う。速さの逆を行く遅さ、つまりスラッジ成分も取り込んでいるところもその手のハードコアに通じるところがある。いわゆるアンビエント、アトモスフェリック、ポストといった形容詞が表現するともすると冗長、高尚になってしまう要素に関してはこれを余計な夾叉物として一切を排除する。いわば極悪非道なハードコアなのだが、よくよく考えてみるとこういったピュアなバンドというのはなかなか日本にはいないかもしれない。もっと先鋭化してパワーバイオレンスの荒涼とした地平にひたすら残虐性とヘイトを求めるか、もしくは日本人の真面目さを反映した悩み多き鬱屈さを追求するエモバイオレンス方面のハードコアに舵を切るか、その二択のいずれかを選択するようなバンドが多い気がする中、あえてピュアなハードコアを鳴らすというのは結構稀有ではと思う。
ただまったくもって北欧スタイルを金沢で再生したのがTHE DONORかというとそこが少し違くて、そしてそこがこのバンドの面白いところ。激しい音楽に抒情性を混ぜ込む、というのは陳腐な言い回しだが、実際にやるとなるとある程度手法は決まっていて、そういった意味では日本の激情はその手の表現が得意である。THE DONORはここを別の手法で攻めていて、感覚的にはトレモロに感情を込めるブラックメタルに似ているが、そこまでわかり易くないのが、チャレンジンクで面白いし、仕上がりが絶妙に格好いい。そういった意味では3LAのコンピ「ろくろ」に提供した「kagerou」はやはり白眉の出来では。コンピとアルバムでは別バージョンになっており違いを楽しむことができる。とにかくアウトロの放り出すような、ヤケクソめいた表現が曲の終わりってことで最高のクライマックスになっている。
いわゆるジャパニーズスタイルのハードコアが激しい音楽性にいろいろな形で豊かな表現を取り入れたとしたら、やはりこのバンドもその系譜にあるということだろうか。
前作をまっとうにアップデートさせた素晴らしい内容でこの手の音楽が好きなら聞き逃す手はない非常におすすめしたい音源。この音源とそれに伴うライブの後、THE DONORは年内での活動休止をアナウンスしている。非常に残念なことだ。視聴できるところが見つからなかったので買って聴いてください。
ダン・シモンズ/ハイペリオンの没落
アメリカの作家によるSF小説。
「ハイペリオン」から始まる4部作の第2弾。一応この4部作は2つに分けることができるので、ここで一旦「ハイペリオン」から始まった物語に片がつく。
意を決して時間の墓標に足を踏み入れた6人の巡礼たち。しかし肝心のシュライクは顕現しない。やきもきする一行をよそに惑星はるか上空での連邦ヘゲモニーと宇宙の蛮族アウスターとの決戦は激化の一途をたどる。思いがけない方法によってウェブ内にアウスターが進行していることがわかり、連邦はその存続の危機に立たされることになる。
大団円に向かう前にとにかく大風呂敷を広げまくるダン・シモンズ。矢継ぎ早に連邦は危機に立たされることになる。前作では巡礼6人がそれぞれ別個の物語を旅の途中で語る、という形式だったため、作者があえて6つの物語を異なるジャンルと言ってほどのバリエーションを持たせて1冊の本にした入れ子構造がまるで「ハイペリオン」という本を連作短編集のようにしていた趣があったが、今作では過去が一通り語られたあとで物語が未来に向かって一直線に動き始める。視点の転換はさすがにあるものの、概ね主人公というのが巡礼とその他に設定されており、ある程度固定化された視座から物語を読者が俯瞰できる。
また合う人類属する連邦対アウスターの宇宙を舞台にした戦争が物語の中心を貫いており、スケール感がアップ。巨大な連邦が窮地に陥っていくさまはなかなかのスリルがある。
とにかく物語よく練られていて最近ありがちなどんでん返しだけで目を引く、オチだけで長いページを持たせる系のとんでもSF(謎がいっこしないのはいいとしても、それありきのストーリーが予定調和でむりがあって全然しっくりこない)やセンセーショナルな状況ややたらと個人の判断が世界の行く末を判断する、薄っぺらい残酷さなどで悪目立ちする軽薄な小説群とは明らかに異なる、非常にしっかりとして骨組みのある”物語”がある。この物語にどっぷり浸れるのが読書の醍醐味の一つだと思うがそれをもう120%以上満たしてくれる濃厚さ。大森望さんの解説でも書かれているとおり、実はこの「ハイペリオン」というのは全く革新性がない物語なのだが、それでも面白さというのは抜群だ。
思うに人間というのは誰かに操られている、と考えてしまってそれが許せない性質があるらしい。登場人物の一人ソルの例もあるし、「ハイペリオン」でも裏で人類を操る何者かからの開放というのが物語的なカタルシスとして働いている。シュライクというのは特定の登場人物たちによって神の立場崇め奉られているという点も興味深い。実際今息災にやれているなら一体誰に操られていようと気にしなくてもよいのでは?と怠惰な私は思うのだ。西遊記の孫悟空のごとく、お釈迦様の手のひらの上でもかまわないというのが私なのだが、それが仏なら良いが悪鬼羅刹だとかなわないというのはわかる。しかし最終的に偶然を擬人化して暴君のレッテルを貼るのも無理な話で、今自分が何者かに操られている、以内の判断はどうしたら?とも思うわけで、そう考えると宇宙に拡大した人類から一掃されない号の深さのようなものも感じられて面白い。やはり良い物語というのはそのスケールや舞台に関係なく、普遍性というのがその核に閉じ込められていると思う。
数々の謎にもきれいに答えが並べられており、決してハッタリや虚仮威しではない物語の完成度に感服する4部作の前編のフィナーレ。ぜひ「ハイペリオン」からどうぞ。私はもちろん「エンディミオン」からの後半も楽しむつもりである。
「ハイペリオン」から始まる4部作の第2弾。一応この4部作は2つに分けることができるので、ここで一旦「ハイペリオン」から始まった物語に片がつく。
意を決して時間の墓標に足を踏み入れた6人の巡礼たち。しかし肝心のシュライクは顕現しない。やきもきする一行をよそに惑星はるか上空での連邦ヘゲモニーと宇宙の蛮族アウスターとの決戦は激化の一途をたどる。思いがけない方法によってウェブ内にアウスターが進行していることがわかり、連邦はその存続の危機に立たされることになる。
大団円に向かう前にとにかく大風呂敷を広げまくるダン・シモンズ。矢継ぎ早に連邦は危機に立たされることになる。前作では巡礼6人がそれぞれ別個の物語を旅の途中で語る、という形式だったため、作者があえて6つの物語を異なるジャンルと言ってほどのバリエーションを持たせて1冊の本にした入れ子構造がまるで「ハイペリオン」という本を連作短編集のようにしていた趣があったが、今作では過去が一通り語られたあとで物語が未来に向かって一直線に動き始める。視点の転換はさすがにあるものの、概ね主人公というのが巡礼とその他に設定されており、ある程度固定化された視座から物語を読者が俯瞰できる。
また合う人類属する連邦対アウスターの宇宙を舞台にした戦争が物語の中心を貫いており、スケール感がアップ。巨大な連邦が窮地に陥っていくさまはなかなかのスリルがある。
とにかく物語よく練られていて最近ありがちなどんでん返しだけで目を引く、オチだけで長いページを持たせる系のとんでもSF(謎がいっこしないのはいいとしても、それありきのストーリーが予定調和でむりがあって全然しっくりこない)やセンセーショナルな状況ややたらと個人の判断が世界の行く末を判断する、薄っぺらい残酷さなどで悪目立ちする軽薄な小説群とは明らかに異なる、非常にしっかりとして骨組みのある”物語”がある。この物語にどっぷり浸れるのが読書の醍醐味の一つだと思うがそれをもう120%以上満たしてくれる濃厚さ。大森望さんの解説でも書かれているとおり、実はこの「ハイペリオン」というのは全く革新性がない物語なのだが、それでも面白さというのは抜群だ。
思うに人間というのは誰かに操られている、と考えてしまってそれが許せない性質があるらしい。登場人物の一人ソルの例もあるし、「ハイペリオン」でも裏で人類を操る何者かからの開放というのが物語的なカタルシスとして働いている。シュライクというのは特定の登場人物たちによって神の立場崇め奉られているという点も興味深い。実際今息災にやれているなら一体誰に操られていようと気にしなくてもよいのでは?と怠惰な私は思うのだ。西遊記の孫悟空のごとく、お釈迦様の手のひらの上でもかまわないというのが私なのだが、それが仏なら良いが悪鬼羅刹だとかなわないというのはわかる。しかし最終的に偶然を擬人化して暴君のレッテルを貼るのも無理な話で、今自分が何者かに操られている、以内の判断はどうしたら?とも思うわけで、そう考えると宇宙に拡大した人類から一掃されない号の深さのようなものも感じられて面白い。やはり良い物語というのはそのスケールや舞台に関係なく、普遍性というのがその核に閉じ込められていると思う。
数々の謎にもきれいに答えが並べられており、決してハッタリや虚仮威しではない物語の完成度に感服する4部作の前編のフィナーレ。ぜひ「ハイペリオン」からどうぞ。私はもちろん「エンディミオン」からの後半も楽しむつもりである。
登録:
投稿 (Atom)